日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドラインにあるステロイド治療関連記述のまとめ
1)アトピー性皮膚炎の病態
皮膚の生理学的機能異常を伴い、複数の非特異的刺激あるいは特異的アレルゲンの関与により生じる慢性の炎症で、湿疹・皮膚炎群の一疾患。
2)アトピー性皮膚炎の治療の基本(この順で記述されている)
①炎症に対してはステロイド外用薬やタクロリムス軟膏による外用療法を主とする。
②生理学的機能異常に対しては保湿・保護剤外用などを含むスキンケア。
③瘙痒に対しての抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬の内服を補助療法として。
④悪化因子を可能な限り除去する。
なお、アトピー性皮膚炎治療におけるEBMは九州大学皮膚科から「アトピー性皮膚炎ーーより良い治療のためのEBMデータ集ーー」がインターネット上に公開されている。(この中で最も重要視されている論文はFurue 論文で、その治療成績の要点は、表を作り変えて最後に資料として示す。全体の批判はatopic ホームページの「佐藤先生のブログ」に4回に分けて記述している。http://atopic.info/satokenji/ 2010.12.13-2011.2.27まで。なお、最近のブログ2011.11.20NHKの番組について、アトピーに限ってと日本皮膚科学会中部支部学術大会の報告を参照)
「はじめに」の最後は「本ガイドラインを参考にした上で、医師の裁量を尊重し、患者の意向を考慮して、個々の患者に最も妥当な治療法を選択することが望ましい。」で終わっている。そして、「はじめに」の最初は、上記疾患概念と治療ガイドラインは世界的に近似していることと、患者への十分な説明や治療へのコンプライアンス(治療法に従うこと)とアドヒアランス(継続すること)を考慮すべき疾患であることを強調している。
3)予後について
本治療法による予後についての記述は以下のみである。「一般に慢性に経過するも適切な治療により症状がコントロールされた状態に維持されると、自然寛解も期待される疾患である。」この記述には引用文献が無く、根拠のない記述と評価せざるを得ない。もし本当に予後についての記述が根拠のあるものなら、上記EBMデータ集から選んでここで引用できるはずである。
4)治療について
①目標は次の状態への到達である。
「(1)症状はない、あるいはあっても軽微であり、日常生活に支障が無く、薬物療法もあまり必要としない。 (2)軽微ないし軽度の症状は持続するも、急性に悪化することはまれで悪化しても遷延することはない。」
(2)については薬物療法に関する記述が無いが、薬物治療をしていてもあるいは薬物治療によってという気持ちがあると判断できる。患者は目標(2)より目標(1)を希望するだろう。ガイドラインに治療目標(1)があるのであるから、ステロイド治療を行われている患者は、直ちにステロイドを使用しない治療を希望することは一応除外するとしても、ステロイドを使わない治療に向かってほしいということは言えるはずであるし、ガイドラインに従って治療していると主張する医師はこの患者の希望に応えてどのように治療するかを考える義務があるであろう。
初めからステロイドを使用しない治療を希望することはガイドラインに記述されていないように見えるが、これは可能であろうか。また、この治療を拒否することは医師に許されるであろうか。この疑問がこの小文を書く契機である。
②薬物療法
「現時点において、アトピー性皮膚炎の炎症を十分に鎮静しうる薬剤で、その有効性と安全性が科学的に立証されている薬剤は、ステロイド外用薬とタクロリムス軟膏である。」と記されているが、これを裏付ける引用文献は示されていない。しかし、ステロイド外用剤の外用効果については、「ストロングクラス以上のステロイド外用薬では、1日2回外用と1回外用の間に、3週間以降の治療効果については有意差が無い。」ことと「ミディアムクラスの場合には、1日2回外用の方が1日1回外用よりも有効である。」ことに関してのみ引用文献がある。タクロリムスについては4年使用で問題はないとの引用文献がある。しかし、わざわざ「3年以上の長期使用の結果からも重篤な全身性有害事象はなく」と表現されている。意図的な変更である。発癌を考える副作用についてはもっと長期の経過観察が必要である。チェルノブイリでの子どもの甲状腺癌が原子力発電所の爆発事故の後、放射能でさえ4年ほどしてから発癌が増え始めていることを考えれば、まだまだ観察の初期と考えるべきで、安全宣言するべき時期ではない。
③外用中止について
無治療に持っていくためのステロイド減量時に「再燃のないことを確認する必要」を述べている。「炎症症状の鎮静後にステロイド外用薬を中止する際には、急激に中止することなく、症状を見ながら漸減あるいは間欠投与を行い徐々に中止する。ただし、ステロイド外用薬による副作用が明らかな場合にはこの限りではない。」
ある程度の期間ステロイド外用を続けるとステロイド依存性が出てくるので、ステロイド減量時に再燃のない状態で減量ができることは、かなり珍しいことである。この再燃をどうとらえるかがステロイド派と脱ステロイド派の違いの最も重要な点である。
④ステロイドの効果が不十分
ステロイド外用薬は「アトピー性皮膚炎の炎症を十分に鎮静しうる薬剤」と述べられている。にもかかわらず、同じガイドラインにタクロリムス軟膏関連では、「タクロリムス軟膏はステロイド外用薬では治療が困難であったアトピー性皮膚炎に対しても高い有効性を期待し得る。」や「ステロイド外用薬などの既存療法では効果が不十分」な場合にタクロリムス軟膏は高い適応を有する、と言う。また、シクロスポリン(ネオーラル)内服薬関連では、「シクロスポリンの適用となるのは既存の治療に抵抗する成人例で」とある。
同じガイドラインの中に「炎症を十分に鎮静しうる」と「効果が不十分」が共存するステロイド外用薬とはいったい何なのか。この矛盾を解くためには、使用開始時には十分有効であるが、使用が長引くに従って既存の治療では効果が不十分になったり既存の治療に抵抗するようになる現象を考慮しなければ理解できない。すなわち、2000年版では言及されていた「ステロイド抵抗性(連用による効果の減弱)の事象」やステロイドに対する依存性の存在を承認しなければならないのである。
⑤ステロイド外用薬の副作用に対する誤解
(1)ステロイド内服薬と外用薬の副作用の混同
(2)アトピー性皮膚炎そのものの悪化とステロイド外用薬の副作用の混同
これらによりステロイド外用薬への恐怖感、忌避が生じ、コンプライアンスの低下がしばしばみられる。十分な診察時間をかけて説明し指導すれば治療効果を上げることができる、と述べている。(2)についてはステロイド依存性皮膚症との関係で非常に重要な記述ではあるが、引用文献はない。
ステロイドの局所的副作用として、ステロイド痤瘡、ステロイド潮紅、皮膚萎縮、多毛、細菌・真菌・ウイルス性皮膚感染症などを挙げているが、酒皶様皮膚炎は挙げていない。問題となるステロイド依存性皮膚症の顔面版である。しかし、ステロイドで起こることが分かった後で明らかになったタクロリムスでの酒皶様皮膚炎は記述されている。ステロイドで記述されていないのはステロイド依存性皮膚症に注意を向けないための意図的除外である。2000年版アトピー性皮膚炎治療ガイドライン(川島真、他、日皮会誌 2000; 110, 1099-1104)には、「ステロイド抵抗性(連用による効果の減弱)の事象も通常の使用では経験されない。」とあるが、その次の「日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎治療ガイドライン2003改定版(古江増隆、他、日皮会誌 2003; 113: 119-125)」以降は削除されている。これも、同じ目的の行為である。
⑥ステロイドを使用しない治療
この治療について明言は避けているが、次の記述がある。「その他の特殊な治療については、一部の施設でその有効性が強調されているのみであり、科学的に有効性が証明されていないものが多く、基本的治療を示す本ガイドラインには取り上げない。むしろ、その健康被害の面に留意すべきである。」と。ガイドラインのスピーカーである東京逓信病院皮膚科E医師は、2011.6.11-12開催の第27回日本臨床皮膚科学会で、「多くの患者さんが…脱ステロイド療法などにより、多大な弊害を被っている。」(抄録)と発表している。特殊な治療すなわち脱ステロイド治療は、皮膚科学会の妨害をはねのけて一部の施設で行われ、その有効性のゆえに多くの患者がごく一部の施設に押し寄せているのである。皮膚科学会が頑なに事実を見ようとせず、ステロイド治療を中止すればほとんどの重症患者さんが救われるのに、危険な免疫抑制剤の使用を拡めているのは患者にとっては大変困ることである。また、高額であるため医療経済にとっても困ることである。
第1回アトピー勉強会資料1
11月 28th, 2011 | Posted by in 講演会You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.
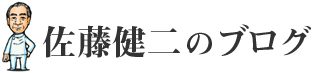


Leave a Reply