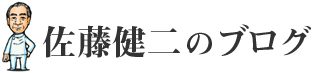古江論文批判 4 (主として副作用について)
Furue M et al
Clinical dose and adverse effects of topical steroids in daily management of atopic dermatitis
British Journal of Dermatology 2003; 148: 128-133
アトピー性皮膚炎の日々の治療における外用ステロイドの臨床用量と副作用
1.副作用関連の本文記述
Furue論文にある副作用に関しての記述は次の通りである。
論文の要旨の項には次のように記されている。「副作用については、頬の毛細血管拡張の発症率は、より罹病期間が長い、6か月の治療期間中に顔面に20g以上を塗布した患者において増加する傾向があった。ステロイドで作られた、肘窩膝窩の萎縮は、女性より男性で高頻度に存在した。」とある。
はじめにの部分では「外用ステロイド、保湿剤、内服抗ヒスタミン剤が第一選択薬としてアトピー性皮膚炎に用いられているが、外用ステロイドの長期使用の怖さは、世界中で多くの患者に外用ステロイド恐怖症を生んでいる。しかし、診療所で治療されているアトピー性皮膚炎患者に対する外用ステロイドの臨床用量と副作用についての情報はほとんどない。これらの点を明らかにするために、我々は少なくとも6ヶ月間経過を追われてきた1271人のアトピー性皮膚炎患者の臨床データを分析した。」と述べている。
材料と方法の項では「頬の毛細血管拡張、肘窩・膝窩の皮膚萎縮、痤瘡と毛嚢炎、多毛、細菌感染、皮膚真菌症、酒皶様皮膚炎、外用ステロイドによる接触皮膚炎、ステロイドによる線条皮膚萎縮症」を調べたとある。統計分析には次のように記されている。「性別、年齢、罹患期間、外用ステロイド6ヶ月間塗布総量、異なる強さのステロイド6カ月塗布量(最強+上強+強と中等+弱)が3つの主要な副作用に与える影響を断片化線形モデルを用いた逐次ロジスティック回帰分析(訳者注:この訳でいいかどうか不明。また、内容も訳者には理解できない)で解析した。罹患期間と6カ月の塗布量は断片化線形変数として取り扱い、これらの変数に対して、それぞれ1年と10gの間隔で一つの変化点を持つ替え玉変数が解析に用いられた。各変化点に対する替え玉変数は最大値(0、本来の変数―変化点)と定義された。」
結果の項目には、「外用ステロイドの副作用」と題して以下の記述がある。「外用ステロイドを塗布すると、皮膚で、多毛、毛細血管拡張、皮膚萎縮のような軽い可逆性の副作用が起こる。高度の皮膚萎縮があると、ときにより重症の不可逆的副作用である線条皮膚萎縮症が起こる。これらの副作用の累積発症率は、累積ステロイド塗布量に相関すると想像されたが、各患者で発症後の累積ステロイド塗布総量を知ることは困難である。しかし、我々は、6か月の外用ステロイド量と累積総量の間に相関があると推測した。副作用の累積発症率を評価した(表5)。予想した通り、副作用の累積発症率は、幼児アトピー患者より青年成人アトピー患者ではるかに高かった。頬の毛細血管拡張、肘窩の皮膚萎縮、膝窩の皮膚萎縮は、しばしば観察される副作用である、なぜなら、アトピー性皮膚炎の好発部位は顔と屈側領域であるからである。次に我々は、上で述べた3つの主要な副作用に対して、断片化線形モデルを用いた逐次ロジスティック回帰分析を使用して、性別、年齢、罹病期間、6か月の外用ステロイドの総量、および6か月の異なったランクのステロイド量(最強+上強+強と中等+弱)のオッズ比を解析した。頬の毛細血管拡張については、我々は次のことを見出した。ⅰ.発症率は、患者の年齢が高くなると高くなる傾向であった。すなわち、幼児<小児<青年成人である。ⅱ.発症率は、罹病期間最初の6年間、オッズ比は毎年1.8倍増加したが、6年以降は増加が止まるか低下さえした。ⅲ.発症率は、顔面に塗布される外用ステロイドの量が6カ月で20gを超えると徐々に増加した。肘窩の皮膚萎縮については、我々は次のことを見出した。ⅰ.発症率は、患者の年齢がより高くなると増加する傾向であった。すなわち、幼児アトピー<小児アトピー<青年成人アトピーである。ⅱ.発症率は、罹病期間初期9年間、オッズ比は毎年1.2倍増加したが、9年以降は増加が止まるか低下さえした。ⅲ.発症率は女性より男性で高かった。ⅳ.発症率は、体幹と四肢に塗布された”最強+上強+強”のステロイド量が6ヶ月間で500g以上だと徐々に増加した。膝窩の皮膚萎縮については、我々は次のことを見出した。ⅰ.発症率は、罹病期間初期9年間、オッズ比は毎年1.3倍増加したが、9年以降は増加が止まるか減少さえした。ⅱ.発症率は女性より男性で高かった。ⅲ.発症率は、患者の年齢が高くなると増加する傾向であった、すなわち、幼児アトピー<小児アトピー<青年成人アトピーであった(表6:省略)。」
表5 外用ステロイドの副作用(%)(訳者にて改変:表2の患者数をもとにそれぞれの副作用の群別と全患者の数を計算で出した。)
幼児 小児 青年成人 合計
年齢群 <2歳 2歳≦ <13歳 13歳≦
患者数 210 546 515 1271
% (実数) % (実数) % (実数) % (実数)
多毛 0.5 1 1 5 2.7 14 1.6 20
頬の毛細血管拡張 0 2.3 13 13.3 68 6.4 81
肘窩の皮膚萎縮 1.5 3 5.2 28 15.8 81 8.8 112
膝窩の皮膚萎縮 1.9 4 4.1 22 9.8 50 6.0 76
線条皮膚萎縮症 0 0 1 5 0.4 5
痤瘡と毛嚢炎 0 1.3 7 8.2 42 3.9 49
細菌感染 1.4 3 2.1 11 2.5 13 2.1 27
真菌感染 1.9 4 0.6 3 1.2 6 1.0 13
ステロイド誘発皮膚炎 0 0.4 2 3.1 16 1.4 18
接触皮膚炎 0 0.4 2 0.8 4 0.5 6
考察の項目では以下の記述がある。「外用局所で活性のあるステロイドの臨床的有用性は、その抗炎症活性に照らして、また経皮吸収から起こる全身的副作用だけでなく好ましくない局所の副作用を起こす性質に照らして評価されなければならない。外用ステロイドは、色々な臨床的重症度の慢性アトピー患者に広範に用いられている。患者は、病気がほど良く調節されている状態の時より、ひどく悪化している時の方がより多くのクリームや軟膏を使用するようである。従って、病院や診療所で普通に処方される、色々な量のステロイド製剤の効果と副作用を研究することは重要と思われる。これまでの研究では、副腎系の抑制は普通量の外用ステロイドを用いている外来患者では重要でないことが示されている。
外用ステロイドは、毛細血管拡張、皮膚萎縮、多毛、色素減少、口囲皮膚炎、真菌・細菌・ウイルス感染、線条皮膚萎縮症のような外用局所皮膚での種々の副作用を生む。線条皮膚萎縮症を除いてこれらの副作用は基本的には軽症で可逆的なステロイドの副作用である。しかし、長期間の外用ステロイド塗布によって起こされた、局所の副作用発症率は知られていない。
この研究で、我々は、外用ステロイドの臨床用量と副作用を調べた。多くの患者はこの研究が始まる前にステロイドを使用していたことと、教育、激励、その他の色々な治療をしてきていたことが強調されなければならない。だから、改善上の変化をステロイドだけに帰すことは非常に難しい。
………
この研究では、患者のアトピーの罹患期間は1カ月から79年で、その中央値(第25百分位数、第75百分位数)は3.0年(1.1年、7.0年)であるので、患者は長期に外用ステロイドを塗布していたと思われる。この推測を支持するように、ステロイドで作られる毛細血管拡張や皮膚萎縮の発症率は、患者の年齢が高くなると多くなる。局所的皮膚萎縮や毛細血管拡張のような副作用を持つ患者は、率は少ないが認めうる程度には存在した。これらの副作用の発症率は、年齢、性、外用ステロイドの強さと量で予測することができるかもしれない。」以上で古江氏の記述は終わりである。
2.重要な補足説明
「ⅰ.発症率は、患者の年齢が高くなると高くなる傾向であった。すなわち、幼児<小児<青年成人である。ⅱ.発症率は、罹病期間最初の6年間、オッズ比は毎年1.8倍増加したが、6年以降は増加が止まるか低下さえした。」この関連を理解するには、3次元のグラフを書くと分かりやすい。横軸に年齢、縦軸に患者数、奥行き軸に罹病期間を取る。まず横軸と縦軸だけを見て、幼児群・小児群・青年成人群に分けて副作用発症者をみると、青年成人群で非常に多くなっている。そこで、各群の奥行き軸に手前から罹病期間1年目の副作用発生患者数、2年目の副作用発生患者数、3年目の副作用発生患者数—-と奥に向かって罹病期間別に患者数を振り分けてみると、頬の毛細血管拡張では6年目までは順調に増加するがそれ以降、罹病期間が長くなると患者数が減り、肘窩・膝窩の皮膚萎縮については9年目を境に増加から減少に変わるということである。この変化は青年成人群で最も明瞭に出ているであろう。
3.補足説明の重要さについて
古江氏は、副作用の発症では、主として頬の毛細血管拡張と肘窩・膝窩の皮膚萎縮に絞って検討している。彼は、副作用の累積発症率は累積ステロイド塗布量に相関し、6か月の研究期間に使用したステロイド量は各患者が発症から使用してきたステロイドの累積総量と相関があるという前提に立っている。アトピー性皮膚炎は幼少期から発症することが多いので、年齢が高くなれば累積外用量も多くなるのは当然である。このことを示すように、研究結果は、幼児・小児・青年成人と大きく群として分ければ予想通り高年齢群で副作用の発症率が高かった。もしこれだけのデータであればその通りの内容を書くだけで十分であろう。しかし、問題がある。年齢群別に分ければ高齢者で多いが、同じ年齢群の患者だけを取り出し(合計で見ても同じ結果であるが)発症後の罹病期間別に発症率を見れば、頬の毛細血管拡張と肘窩・膝窩の皮膚萎縮の発症率は、毛細血管拡張で発症から6年、皮膚萎縮で発症から9年経つと低下することである。ある年齢を過ぎてまだ、病気が続いているのであるから、外用量も増え、発症率は増加しなければならないにもかかわらず、減少しているのである。この結果は予想と違っているわけであるから、自分の前提的考え方との違いを説明あるいは弁明しなければならない。これについては論文中には見当たらない。逆に、要旨には結果と矛盾するような内容が記述されている。すなわち、「頬の毛細血管拡張の発生率は、より長期の罹病期間を持ちかつ6カ月の治療期間中に顔面に20g以上を塗布した患者では増加する傾向があった。」(下線は訳者。結果の項では患者の二つの条件は並存条件ではなく別々に述べられている。ここでは長期の罹病期間と20g以上という並存条件のある場合のことを述べているので、正しく結果を示しているかもしれない。しかし、結果で述べられている、より長期の罹病期間を持つ患者では発症率が低下することが隠されている。)少なくとも、罹病期間と発症率に関して述べるならば、長期罹病の人では副作用発症率が減少することを述べる必要があった。
外用量が増えれば副作用が増えるのであるから、副作用が減るためには外用量が減らなければならない。罹患期間の長い人の中では副作用の発症が減ったのであるから、外用量を減らしたことになる。外用量を減らすには、症状がよくならなければならない。もしそういう相関が傾向としてでも見られたら記述したであろう。しかし、その記述の無いことをみると、このことは起こっていないと判断しうる。病勢が改善している率は少なく同じ状態で維持されている率が高かったことからもわかることである(治療後の重症度分類が同じである率が非常に高かった)。この二つを合わせて考えれば、副作用が出てきているので外用は減らさざるを得ない、かといって減らせば症状はよくならない、という臨床医の行き詰まり状態を示していると考えるのが現実を正しく示しているであろう。従って、要旨などの「外用ステロイドはアトピー性皮膚炎治療のためには有益である」と言うには余りにも貧相な結果であることの一断面を副作用の経過が示していると言えよう。
注
これまでの私の見解では、発症率という言葉を、古江氏の使い方通りに使ったが、古江氏の論文の中で発症率(incidence)という言葉はいくつかの意味に使用されている。この説明に入る前に発症率(incidence)と罹病率(prevalence)の意味をいくつかの辞書から引用する。以下に示すように、医学用語として、incidenceは罹病率・罹患率・疾病率・発病率・発症率等と訳され、prevalenceは有病率と訳される。しかし、incidenceは、一般の用語として何かが起こる率を示す「発生する率」としても使用され、prevalenceは頻度が多いという一般的な意味で使用されることがある。
# kotobank.jpによれば
罹病率(=発病率):ある期間の疾病発生件数のその期間内平均人口に対する割合(百分率)。ただし、年率の場合は人口1000人当たり、疾病別の場合は人口10万人当たりの数値を用いるのが普通。
有病率:ある時点における病気・けがをしている人の、人口に対する割合
# 大辞林初版によれば
罹患率:一定期間に発生した特定の疾病の新患者数の、その疾病にかかる危険にさらされた人口に対する比率。普通人口10万人当たりの数値で示す。罹病率、疾病率。
有病率:ある時点、ある地域内に存在する全患者数をその地域の人口で割ったもの
# Stedman’s Medical Dictionary (24th Ed)では
incidence: The number of new cases of a disease in a population over a period of time
prevalence: The number of existing cases of a disease in a given population at a specific time
# Webster’s Third New International Dictionaryでは
incidence: the rate of occurrence of new cases of a particular disease in a population being studied
prevalence: the percent of a population being studied that is affected with a particular disease at a given time
と記述されている。
発症率と有病率を私の言葉でいえばこのようになる。発症率とは、生まれたすべての人の中で特定の病気にかかる人の率である。有病率とはある時期に特定の病気にかかっている人の率である。だから、ある病気が途中で治り消えてしまう病気であれば、その病気が何らかの理由で治りにくくなれば、その病気の発症率は同じでも有病率は増加することになる。アトピー性皮膚炎は、昔は85%が成人期には消失していた。だから、発症率と有病率は明瞭に区別して議論しなければならない。
4.発症率(incidence)という言葉の使い方
Furue論文の「はじめに」の部分でアトピー性皮膚炎が増えていることを述べているが、古江氏が引用している報告は、有病率(prevalence)が増えていると言っているだけであり発症率(incidence)が増えているとは言っていない。論文の調査方法を見ても、有病率が分かる調査であり、発症率が分かる調査ではない。にもかかわらず古江氏は発症率(incidence)が増えていると述べている。もし単純にincidence とprevalenceの違いを知らなかったというならば、大学教授として問題であるが、古江氏がこの違いを知らないはずはない。わざわざ変える理由は何であるのか。英文チェックの時に変更されてしまったのかもしれない。深くは追及しないでおこう。古江氏は、本論文中では発症率(incidence)について、「はじめに」の部分以外では有病率に近い意味で使用している。すなわち、「ある特定の人々の中で特定の副作用を有する人の割合」という意味に使っている。
なぜこのような使い方をしたかはご本人に聞かなければ分からないが、発症率と有病率を曖昧にし、副作用によって増えていることを初めから除外しようとする考えを入れるための伏線かもしれない。1970年代後半に、ステロイドに対する依存性が外用ステロイドの副作用として報告されている。この副作用はアトピー性皮膚炎と区別がしにくいが、外用を減らせば改善する。現在のアトピー性皮膚炎が増えていると考えられているのはこの副作用がいつまでも残るためである。このことが明らかになることを避けるための一手段と考えることができる。
5.ステロイド誘発性皮膚症(steroid-induced dermatitis)の記述
副作用の調査には「酒皶様皮膚炎」が調べられることになっていた。発生していた副作用の表5には、「ステロイド誘発性皮膚症(steroid-induced dermatitis)」とある。考察の項に、一般論として副作用の一つとして「口囲皮膚炎(perioral dermatitis)」が記載されている。少なくとも酒皶様皮膚炎や口囲皮膚炎の二つが調査票に記載されていたために「ステロイド誘発性皮膚症」の表現が用いられた可能性がある。言葉の使い方は問題にしなくてもいい。しかし、もしステロイド誘発性皮膚症(依存性皮膚症)が報告されていてそれを記述していないならば問題ではある。
ここでは、ステロイド誘発性皮膚症の治療について何も記述されていないことである。この副作用名が出ればステロイドを中止することが治療の第一歩である。それを旨く出来たかどうかが皮膚科の臨床レベルの評価基準となるであろうが、それについての記述が無いため評価ができない。
論文を評価してきての短い感想
「外用ステロイドはアトピー性皮膚炎治療のためには有益である」と自信を持っているかの如く主張されておられるが、重症度分類で改善したのが38%しかない治療成績では、私ならそのようなことはよう言わんな、というのが感想である。まら、論文は良く考えられていて、自分たちの主張に合わない点は巧妙に避けて記述されている、という感も強い。