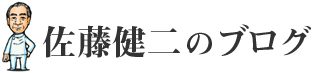ITSANから以下のメールが届きました。重要な内容ですのでお伝えいたします。
Calling TSW Warriors in the DC, Maryland and Virginia area!
The National Institutes of Health (NIH), is conducting a pilot study of Topical Steroid Withdrawal Syndrome with the aim of examining how TSW Syndrome differentiates from eczema, and the adverse impact topical steroids have on some people. This study will perform in-depth analysis of samples from 5 -7 individuals including; skin biopsies, blood and DNA.
ワシントンDC、メリーランド、バージニア州在住者への呼びかけ
アメリカ国立衛生研究所は外用ステロイド離脱症状(TSW syndrome)について予備的研究を行っています。目的は、外用ステロイド離脱症状が湿疹(この場合はアトピー性皮膚炎)とどのように区別されるかと、好ましくない強い影響のある外用ステロイドが一部の人にどのように影響を与えるかについて調べることです。この研究は5-7人の人で皮膚生検し、血液、DNAを取り詳細に分析されます。
(英語訳は不確かです。あまり見ない表現がありますので)
佐藤健二のコメント:
アメリカのNIHがついにアトピー性皮膚炎とステロイド離脱症状との鑑別をどうすれば良いかについて検討し始めました。
私が考える鑑別の項目:
ステロイドの効果が減弱すること(強い薬が必要になることや外用頻度を上げる必要があること)
外用中止で皮疹が拡大すること
アトピー性皮膚炎の好発部位以外に広範に皮疹が拡大すること
好発部位特に肘窩や膝窩での苔癬化の不明瞭化
皮疹は湿潤傾向が強いこと
限局的な苔癬化の場合辺縁の隆起はなだらか
これ以外にご意見があればお教えください。
#ステロイド依存
#TSW
#ステロイド離脱症状とアトピーとの鑑別